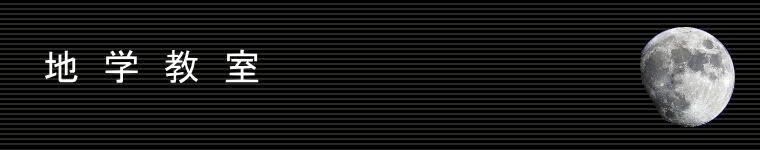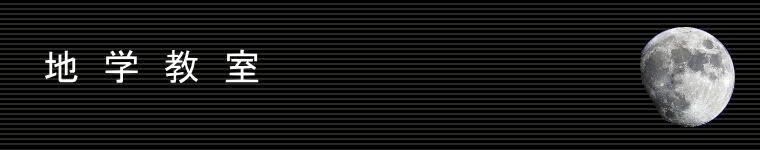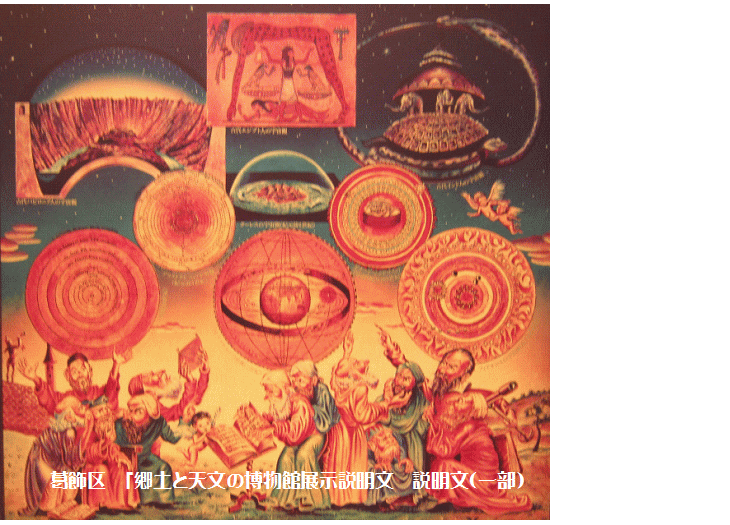 
①
古代インド人の考え
大地が亀や象によって支えられていると考えられていた。その時代、亀や象は飛び抜けて優れた存在と思われていた。
②
古代バビロニア人の考え
大地を海がドーナッツ状に取り囲んでいる。さらに海の周りは山脈が取り囲んでいる。山脈は空や星がある天空を支え、山脈を越え た部分は(外側)は特に考えなかった。
③
古代エジプト人の考え
天空は女神「ヌート」の身体で星々は身体から垂れ下がる飾り-とされた。
④
ターレスの考え(BC6C頃)
宇宙全体は「水」からなる
⑤
アナクシマンドロスの考え(BC6C頃)
地球が宇宙の中心であり、円柱形でその外側は火で満たされている。様々な間隙がありそこから見えるあかりが太陽であり月
である。
⑥
フィアオロスの考え(BC6C頃)
地球や太陽を含む全ての天体が、目に見えない宇宙の中心の火の周りを回転している-と考えた。
⑦
アリストテレスの考え(BC4C頃)
大地は球体でその周りを太陽、月、惑星、恒星が回っている天動説を主張した。
⑧
プトレマイオス(AD2C頃)
天動説をもとに天体の動きを数学的に説明した。
⑨
コペルニクス(AD16C頃)
太陽を中心としてその周りを惑星が回る地動説を主張。

コペルニクス肖像(葛飾区 「郷土と天文の博物館」)
おことわり:写真と説明文は「葛飾区 郷土と天文の博物館」の展示及び説明文によりますが、一部編集しています。
|